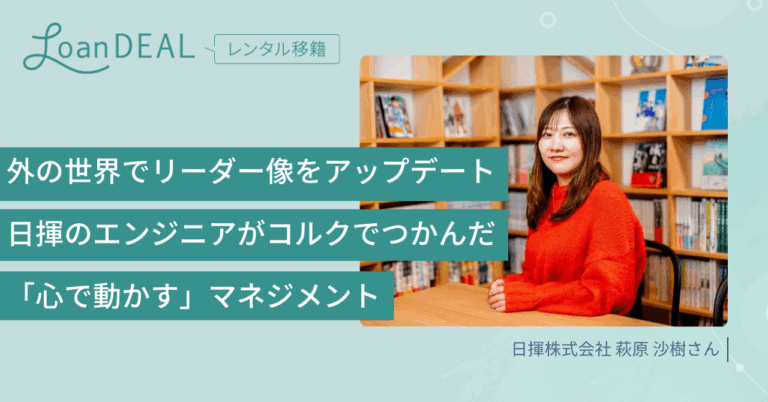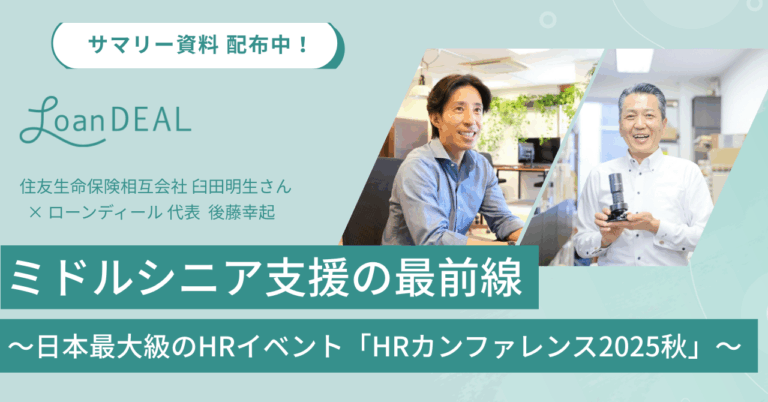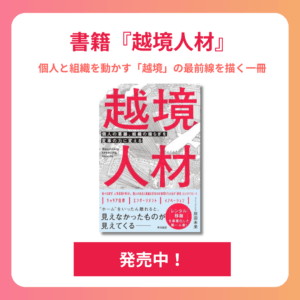迷ったらこれ!自社に合った「越境プログラム」の選び方 【コラム vol.2】

約8割の企業が重要視していると言われている「越境学習」(出典:「日本の人事部 人事白書 2022」5,200社に調査)。「越境学習」とは、企業に所属する人材がその組織の枠を越えて学びを得ることの総称です(詳しくは「越境学習とは?」の記事をご覧ください)。
このコラムでは、越境学習を100社以上に提供しているローンディールがこれまで経験してきたことや、私自身が越境学習施策を企業人事の実務担当者として設計導入した体験談をもとに、「今後、越境学習を導入したい」という企業人事の方に向けて、自社に適した越境学習の選び方やスムーズに導入する方法などお伝えしています。
こんにちは。ローンディールの野島朋子です。
私は2005年に都内百貨店に新卒入社し、10年以上現場を経験した後、人事部に異動。ベンチャー企業への越境研修を担当しました。2020年石川県小松市に移住し退職後、ローンディールの理念に共感し2021年より参画。現在はフルリモートでレンタル移籍のプロデューサーとして勤務しています。
今回は「自社に合った越境プログラムの選び方」についてお話しします。
→ 前回のコラム「最近話題の「越境学習」を導入したい!どこから考えて、どう選べばいい?」はこちら
目次
ーバリエーション豊富な越境学習プログラム。特徴と効果を知って最適な選択を
現在、世の中には非常に多くの越境学習プログラムが存在しており、「どのプログラムを選べばよいか判断がつかない」という声をよく伺います。
導入のしやすさや運営体制なども選定基準の一つではあると思いますが、まずは以下の3つの観点
① 越境先をどこにするか?
② 越境期間をどうするか?
③ どんな経験をさせるか?
を押さえておくことで、自社にとって適切なプログラムを見極めやすくなるでしょう。
そこで、ここからは、
・「越境先の特徴」とそれぞれの効果
・「期間の長短」とそれぞれの効果
・「実践度合い」とそれぞれの効果
について説明していきます。
なおここでは、MBAや大学院といったいわゆる「学び主体以外」のものを扱います。
① 越境先をどこにするか?越境先の特徴と効果の違い
主に越境学習のフィールドとしては大きく次のようなものがあります。
(1)グループ外の大手企業
(2)スタートアップやベンチャー企業
(3)地域やソーシャルセクター
それぞれの効果の違いについてポイントになるのが、企業規模と現業との距離です。
現業との距離とは、業界業種や顧客特性、ビジネスモデルなど、共通するところが多ければ多いほど距離が近いと考えます。また、取引先であるとか出資先であるといった場合も近い距離と考えます。
距離が近い越境先であれば、元々のスキルが生かしやすいですし越境先の理解も早いでしょう。学びや経験を生かしやすいという利点もあります。
逆に遠ければ、キャッチアップに時間はかかりますがその分新たな知見が増えます。これまで自社になかった考え方ややり方、ネットワークを持った人材が社内に増えることで、新しい発想や価値創造につながるでしょう。
ここから、先ほど挙げたそれぞれの越境先の特徴と得られる効果をお伝えします。
(1)グループ外の大手企業
元々のスキルが生かしやすく、越境先でも早期に馴染むのが特徴です。同じ大手でも異なるやり方が学べる・協業しやすいなど、越境した学びをすぐに自社に取り入れられることも多いです。
他方、大手企業は組織規模が大きく、すでに確立された文化や仕組みがあるため、環境としての共通点が多く、求められるスキルセットや価値観も似ていることが多いです。そのため、異なる業界や働き方に大きく触れる機会は比較的少なく、新しい挑戦の幅が一定の範囲に収まりやすい傾向があります。
(2)スタートアップやベンチャー企業
組織の規模が小さくリソースが限られるため一人の果たす役割や経験量が段違いに大きくなるのがこのタイプの越境先です。経営者と日常的に会話が可能な環境も多いため、スピード感や経営視点が身に付きます。正解がない中での意思決定の経験は圧倒的な当事者意識や突破力を鍛えます。しかしながら経験したことを「そのまま」大企業に適用することは難しい側面もあります。具体の学びを抽象化し、自社にどう適用できるか言語化することが重要です。
▼ 参考:以下は、レンタル移籍(ベンチャーへの越境)の効果を説明している図です。
ちなみに、ベンチャー企業への派遣の中でも出資先のベンチャーに研修として越境させるケースがあります。同じく圧倒的な経験量やマインド変化が期待できますが、出資元との力関係によって越境先からの率直なフィードバックが得られにくい場合がありますので、人材育成目的で越境させる場合はこの点が注意点です。
(3)地域やソーシャルセクター
地域には様々な社会課題があります。大企業のオフィスにいるだけでは見えない、現場に越境することで問題を自分事化して考える力が身に付きます。また、NPOや地域団体は、行政や市民団体、企業など多様な利害関係者と連携して活動しています。異なる価値観を持つ人々と協働する経験は、ビジネスの場面でも活きる交渉力や調整力を養います。
このように、越境先の規模感や自社との距離の視点で見ると、それぞれ持ち帰れるものに違いがあるので、目的に合わせて組み合わせるとよいと思います。
※ 「海外」という越境もありますが、グローバルな視点やビジネススキルを身につけるうえで海外での経験が効果的であることは、皆さんもイメージしやすいかと思います。今回はこのテーマには触れませんが、また別の機会にお話しできればと思います。
② 越境期間をどうするか?期間の長短と効果
期間についても様々なバリエーションがあります。ここでは期間の長短でどんな違いがあるのか、それぞれ見ていきましょう。
(1)長期間(半年~1年以上)
越境先の一員となりプロジェクトに責任を負う出向型のもの・チームを組んで月数回のMTGやフィールドスタディ等を実施して課題解決に挑戦する兼業型のものとあります。どちらも長期間、越境先の課題に取り組むので、視野視座の拡大・越境先との濃いネットワーク形成・大きなマインド変化や行動変容が期待できます。
(2)短期間(3ヶ月程度)
プロジェクトの内容やコミット度合いにもよりますが、一般的に3ヶ月程度では、越境先で必要な知識の習得や、風土を体感したり自社とは異なるやり方を知ることができます。一定の経験、数回のアウトプットとフィードバックが得られ、自分の強みや弱みを客観的に認識することでその後の学習意欲やキャリア自律度が高まる効果があります。また社外とのつながりを作ることも可能です。
(3)単発(1日~数日)
越境の入口として取り組むケースがあります。これまで越境経験(社内異動なども含めて)がない方にとって、いきなり社外に出ることはハードルが高いでしょう。単発のプログラムであれば、自己理解の促進、変化のきっかけになります。単発のプログラムは多くの方に提供でき、長期の越境に挑戦する動機付けとなることも多いです。
③ どんな経験をさせるか・実践度合いの違いについて
ここまで、越境先と期間についてご紹介してきましたが、ではどんな経験をさせると良いのでしょうか。ここでは大きく2つのパターンでご紹介します。
例えば、
・自社と異なる知見を得る、視野を広げる
・越境先の課題や具体的な取り組み方のインプット
などといった場合は、フィールドワークや他企業との意見交換プログラム・越境先の課題策提案型のプログラムが適しています。こういったタイプは兼業参加など比較的参加しやすいものが多いので、多忙な方や時短勤務者に提供できるメリットがあります。
他方、
・リーダーシップ開発や経営人材育成
・事業開発など実践的なスキルを身に着けてほしい
といった場合は、越境者のアウトプットと自ら行動を起こすことが必須のプログラムにぜひ挑戦してみてください。この場合は越境先への具体的なビジネス貢献が求められますし本人の対応力や高いモチベーションも求められる分、参加者選定のハードルは上がりますが、幹部候補生やリーダー層・イノベーション推進の人材育成には適しています。
二つのパターンをお伝えしましたが、違いは「実践の度合い」です。ここがどの程度かによって、人材の育成効果で得られるものが異なると感じています。
* * *
いかがでしたでしょうか。今回は、越境プログラムの選び方という観点でお伝えしてきました。
ちなみに、ローンディールでは、ベンチャー企業への越境を3つのパターンでご用意しています。
具体的には、
・半年~1年間フルタイムで越境する「レンタル移籍」
・3ヶ月間、業務時間の20%を使って越境する「side project(サイドプロジェクト)」
・ミドルマネジメント層にオンラインで他流試合の場を提供する「outsight(アウトサイト)」
という3つの越境プログラムを展開しています。
それぞれ目的に合わせてご活用いただければと思っています。
プログラムの詳細やご質問などはお気軽にお問い合わせください。もちろん、ローンディールのプログラムに限らず、越境学習全般に関するお問い合わせも大歓迎です。
次回は「実践型の越境プログラムを社内で通すときのポイント」について、私自身の経験も交えながら、お話したいと思います。また次回お会いしましょう。
以上、野島でした!
▶︎ 第1回コラム「最近話題の「越境学習」を導入したい!どこから考えて、どう選べばいい?」