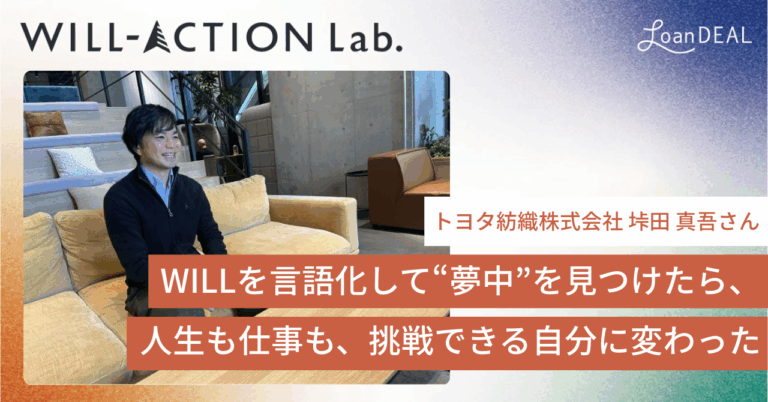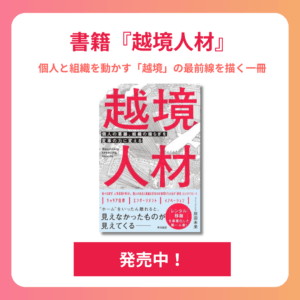経済産業省に根付く「挑戦」の文化と、「レンタル移籍」がもたらす組織・個人の変化

一定期間、所属している組織を離れ、ベンチャー企業の一員として業務に取り組む「レンタル移籍」。新たな環境で価値創造や事業開発に取り組むことができる仕組みで、経済産業省(以下、経産省)でも2018年から導入されています。
公的機関において、いち早くこの仕組みを取り入れた背景には、職員のスキルアップと視野拡大を促し、組織全体の活性化を図るという明確な狙いがあります。
「レンタル移籍」を導入した経緯や狙い、移籍を経験した越境人材に起こった変化や成長について、直近まで経産省で「レンタル移籍」の事務局を担当していた関根友里さん(※2025年7月からこども家庭庁に出向中)と現在担当されている石川なな子さんにお話を伺いました。
(※ 本インタビューは2025年7月にインタビューをしたものです)
目次
民間企業に出向くことで
組織に“多様性”を生み出すことを期待
――経産省では、なぜレンタル移籍を導入されたのでしょうか。
関根:経済産業省には、もともと別の官公庁へ出向する機会等はありました。しかし、ベンチャー企業の方々と肩を並べて仕事をする「武者修行」の機会を設けることで、組織内に多様性が広がり、目まぐるしく変化する社会の中でよりスピーディーに政策を打ち出していくことにつながるのではないか、という考えがありました。
私が携わった時点で、すでにこの制度を導入して6年目になっていましたが、経済産業省にはもともと「今までやっていないことも取り入れてみよう」という文化があるので、レンタル移籍の導入当初も何ら抵抗なく進めることができたのだと思います。

Profile 関根友里さん
2012年経産省入省。これまで主に安全保障、研究開発支援、製品安全、GX等を経験。2人の子育てと仕事を両立中。2年間、秘書課にて人材育成を担当した後、今年7月からこども家庭庁に出向中。
石川:経済産業省の職員の多くは2~3年ごとに部署が変わり、新しい政策分野に挑戦しながらキャリアを積んでいきます。経済産業省の業務とはまったく異なる経験ができるレンタル移籍は、挑戦の選択肢の1つとして、とてもマッチしていると感じます。

Profile 石川なな子さん
2013年経産省入省。これまで主に通商政策やGX等の分野を経験。2024年に長女を出産、約1年の産休・育休期間を経て、今年5月に秘書課人材育成班長として復帰。経産省職員の研修全体をとりまとめ。
――経産省では、数年前にこのレンタル移籍制度を見直したとお聞きしました。
関根:そうですね。参加する職員にとってより効果のある施策にするために、2023年にやり方を見直しました。
省内での公募の方法や派遣する職員の属性などを改めて検討し、現在は、年間を通じて募集していて、立候補してくださった方の中から、所属部署での業務や人事調整のタイミングなどを加味して決めていく形です。
また、省内のイントラネットに募集要項を載せているだけだと気づいてもらえないので、秋頃に翌年の異動希望を書くタイミングで周知しています。自身のキャリアパスについて考える時期なので、新たな挑戦に対する意識も高まりやすいと考えています。
その結果、対象としていた世代において認知が広がりました。
越境したからこそ気づいた
経産省での経験と、自身が発揮できる能力
――関根さんは、クリエイター・エージェンシーのコルクに半年間移籍された岡村さんを最初から最後まで見届けられたそうですね。
関根:移籍中の岡村さんから届く週報を見ていると、とても充実している様子が伝わってきました。新しいことに挑戦するからこその、活気に満ちた状態というんでしょうか。
たとえば、岡村さんはコルク代表の佐渡島さんのルーティーンを真似することで、自身を変えようとしていたんです。その過程で「こんなことを真似して、こう思った」「この部分は、やってみたけど違うと感じた」という声を届けてくれて、岡村さん自身がこれまで経済産業省では経験できなかった経験をもとに、ご自身の成長につなげているのかなと感じましたね。
――週報の中で、印象的な部分はありましたか。
関根:忘れられないのは、岡村さんが書いてくれた「総括能力ってすごいんだということに気づいた」という言葉です。私は思わず、そのメールを保存しました。若手のみなさん全員に伝えたいメッセージだと感じたからです。
官公庁には「総括」という役割があります。課の中で同時並行に進む政策を束ね、全体像を俯瞰し、各チームに橋をかける存在です。いわば、政策現場のプロジェクトマネージャー。若手にとっては必ず経験するポストですが、日々多忙な業務の中でその真価に気づくのは容易ではありません。
多くの若手は「自分こそ政策をつくりたい」という思いが強く、総括の仕事を一歩引いた立場と感じ、意義を見失いがちです。岡村さん自身も当初は疑問を抱いていたかもしれません。しかし岡村さんが「総括能力のすごさ」に気づいた瞬間、それは単なる業務経験を超えて、一つの視座の獲得になったのだと思います。
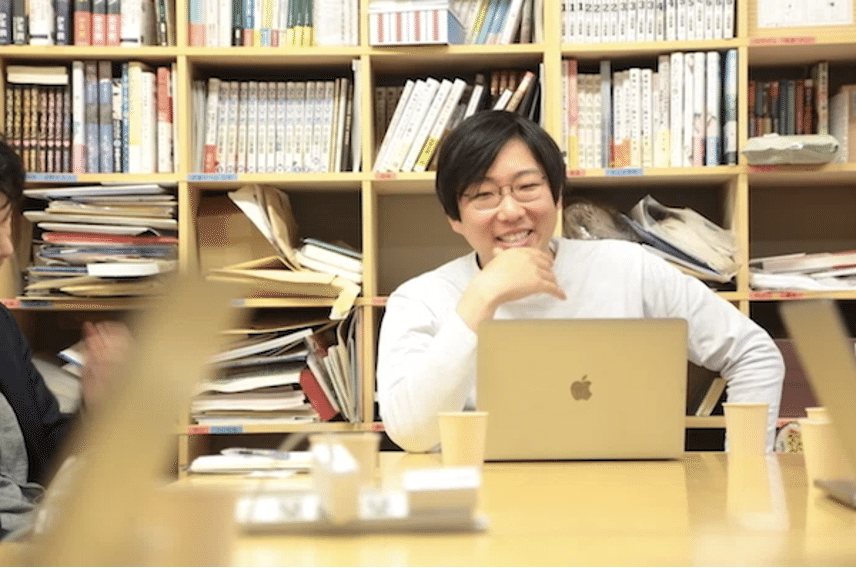
――移籍したことで、自分の仕事の意味に気づけたと。
関根:ベンチャーは意思決定が速く、事業へのチャレンジ機会がどんどん生まれる一方、仕事がスムーズに進まない部分もあると感じたそうで、その原因は「総括=プロジェクトマネージャー」がいないからだと岡村さんは話していました。そして、それこそが自身が発揮できる能力だと気づいたそうです。
官公庁は潜在的に積み上げてきた経験やスキルが見えづらい組織だと感じるのですが、ベンチャー企業という未知の環境に身を置くことで、その経験やスキルを相対的に見ることができるんだと、私自身も教えてもらいました。
石川:私も岡村さんの話を伺って、官公庁とは仕事もカラーも異なるベンチャーで武者修行することによって、自分でも気づいていない強みやスキルを認識できるんだってハッとさせられました。
もちろん、ベンチャーならではの当たって砕けろ精神やビジネス的な考え方などを学ぶことも大切です。これまでの経産省の業務で培われていた潜在的なスキルと新たなマインドセットの両方を認識できるレンタル移籍は、非常に面白い取り組みですよね。
関根:本当は全職員が移籍できたらいいんですが、そうもいかないので、岡村さんをはじめとする経験者が持って帰ってくる声を省内に届けることが大切だと感じています。

――経験者の言葉は説得力がありますよね。戻ってからの岡村さんの活躍ぶりはいかがですか。
関根:戻ってすぐに採用チームの広告戦略などを担当しながら活躍されていましたが、ベンチャーで得てきたスピード感やフロンティア精神のようなものがあふれたアクションを起こしてくれましたね。今は別の仕事で活躍されていますが、さらに意欲的に動いていると思います。
――ちなみに、お二人は越境の経験はありますか。
石川:私は内閣府の沖縄産業振興担当の部署に2年ほど出向したことがあります。6~7人の小さな課室で、それぞれが異なる官公庁から出向してきているところだったので、バックグラウンドが違う前提で情報を共有する方法や、自分自身が舵を取る責任感、判断力のようなものを多少得られたように感じています。
関根:私は14年間経済産業省に在籍してきたのですが、つい最近こども家庭庁に異動しました。初めての経験で、自分が経済産業省の文化に染まっていたことを痛感し、柔軟な対応力や変化を受け入れる姿勢がいかに大切かということを、身をもって経験しています。
官民の垣根を越えたコミュニティで越境学習を広げる
――2025年8月から新たな移籍が始まりますが、移籍者に期待されていることは何でしょうか。
石川:移籍する林さんは通商政策やイノベーション等の分野で経験豊富で、直近まで経済産業政策局で地方創生の一番地に携わっていた方です。これまで得てきた政策の知見や総括的な捌き方・調整力を存分に活かしてほしいです。ベンチャーならではのスピード感やゼロから仕事を作りだす力も体験してきてもらいたいですね。

関根:移籍する方全員に伝えたいことですが、行くからには全力で楽しんでもらいたいですし、「経済産業省ではこうだったな」という発想や着眼点に縛られずに取り組んでほしいです。移籍者ではなくベンチャーの一員として何ができるか、真摯に向き合っていただけたらいいなと。
ーー越境学習の重要性は社会全体で共通するテーマですが、これをさらに広げていくために、お二人がやりたいことはありますか。
関根:私が経済産業省にいる間にやり切れなかったのですが、官公庁と民間企業は異なる組織とはいえ、人材育成やキャリアパスに関する悩みは共通する部分もあると感じています。その悩みを共有できるコミュニティができればいいなと思っています。
人材育成の担当者や越境学習の経験者、これから挑戦したいと考えている人が、官民の垣根を越えて交流できる場です。そこで「越境学習」が重要なテーマの一つとして話されるようになればいいですね。
石川:関根さんの言う通り、他の官公庁や民間企業がどのように人材育成に取り組んでいるのかを知る場は重要です。レンタル移籍についても、得られた知見やその後のキャリアへの影響を共有できれば、この取り組みがもっと広がっていくはずです。

ベンチャーに出向く移籍者を、移籍前の段階から経済産業省に戻ってからもサポートする事務局。その立場にいる関根さん、石川さんだからこそ見える移籍者の変化があります。それは新たな何かを持ち帰るだけでなく、経済産業省で培ったスキルを再認識するという変化でした。スキルを身につけた経緯が明らかになると、経済産業省に戻ってからやりたいことや活躍できる場がより具体的になるはずです。それこそ越境学習の醍醐味だといえるでしょう。
Fin
協力:経済産業省
インタビュアー:有竹亮介
提供:株式会社ローンディール
https://loandeal.jp/