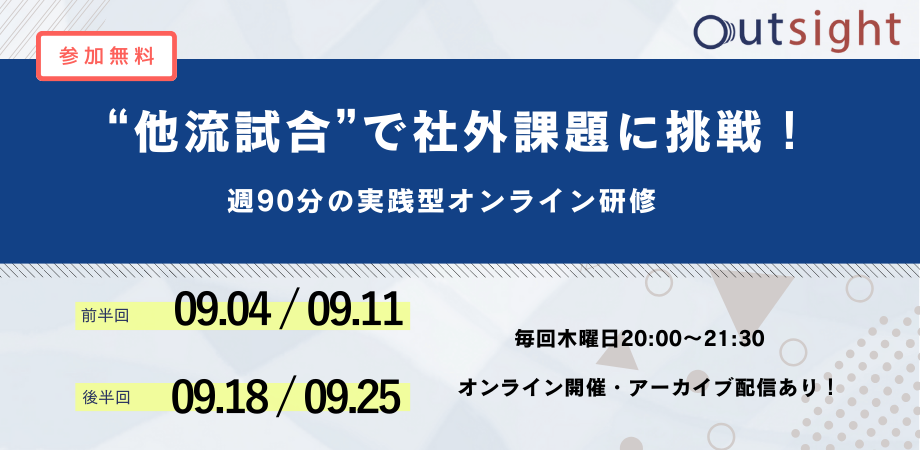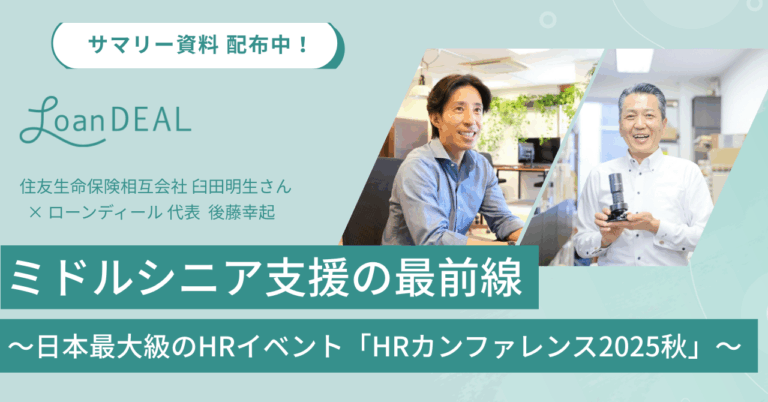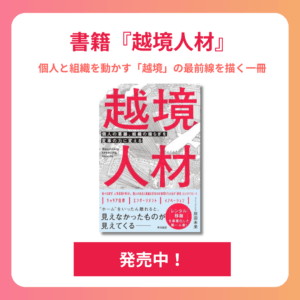「課題は与えられるものではなく、自ら設定するもの」アサヒグループの研究現場がoutsightで鍛えた「アウトプット思考」
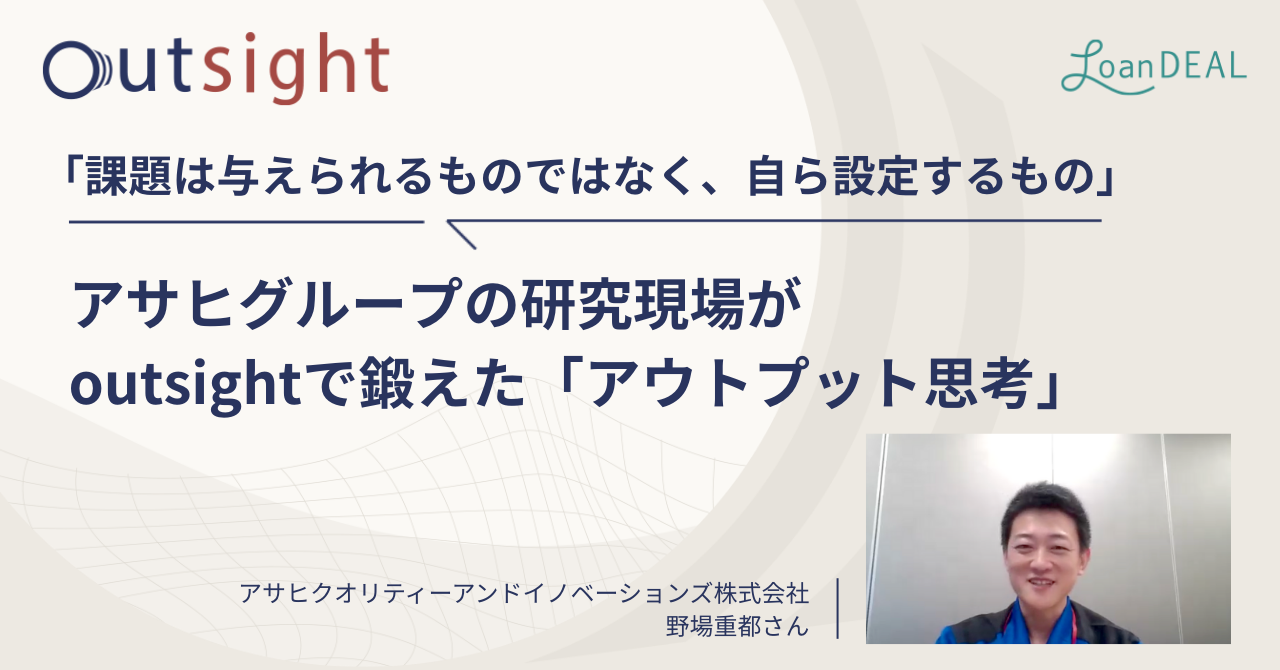
革新的な商品やサービスを生み出すべく、アサヒグループの研究・開発領域を担うアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社。ノンアルコール飲料や新しい嗜好品、健康素材や機能性表示食品、サステナブル技術など、多様な領域でR&Dを推進しています。
特徴的なのは、10年後の理想の社会を描いた「未来シナリオ」を独自に作成し、そこから今すべき研究を逆算するバックキャスティング思考を用いている点。研究者一人ひとりが自らテーマを設定し、高度な専門性を発揮しながら日々研究に向き合っています。
そんな同社の中にある醸造科学研究所が人材育成の仕組みとして取り入れたのが「outsight」です。週に1度、さまざまな領域のベンチャー企業経営者が登壇し、事業課題を共有。受講者は解決策を考えて提案、フィードバックを受けるオンライン越境プログラムです。
同社はなぜ、研究者の育成にoutsightを活用するようになったのでしょうか。outsightで得られたものや、参加者に起こった変化について、醸造科学研究所でマネジメントを担う野場重都さんにお話を伺いました。
(※ 本記事は2025年7月に取材したものです)
目次
課題を「解く力」ではなく、「設定する力」をつけて欲しい
ーー「outsight」導入前、人材育成にどのような課題を感じていましたか。
当社はアサヒグループの研究開発に特化した組織で、研究に関わる社員の約3分の1が博士号保有者の研究者集団です。領域は酒類や飲料、食品にとどまらず、持続可能な社会を実現するため環境技術など多岐にわたります。
研究において大切なのは、「センスのいいリサーチクエスチョンを立てられるか」。これまでにない切り口で課題を設定できるかが勝負だと考えています。筋の良い研究課題があってこそ、良い解決策・商品が生まれるからです。
良い課題設定ができる研究者の育成は当社の重要なテーマですが、これまでの育成方法はOJTが中心でした。
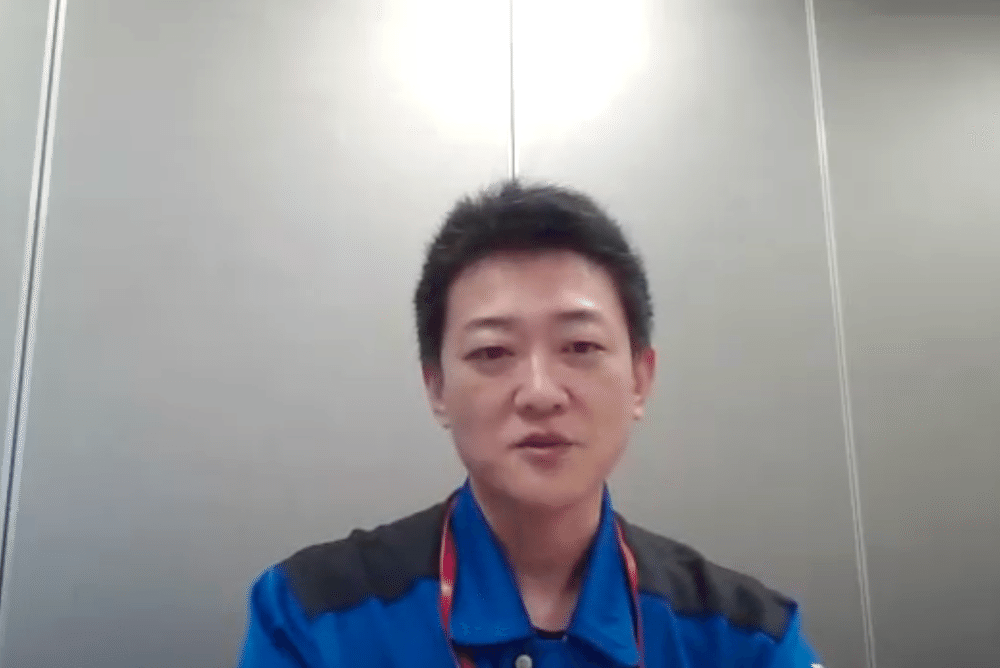
Profile 野場 重都さん
アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 醸造科学研究所第一部長
2006年アサヒビール入社。主としてビールの香味成分に関する研究を担当。2020年よりアサヒクオリティーアンドイノベーションズへ異動し、中長期的な飲料商品技術開発に従事。2021年に博士号を取得。2023年より現職。
ーー課題は会社から与えられるものではないということですね。
そうですね。たとえば「ノンアルコールビールを強化したい」といった大きな方針は提示されますが、そのために何を研究テーマとして設定するかは一人ひとりの研究者に委ねられており、現場からのボトムアップで決まります。
私の所属する醸造科学研究所では、お酒やノンアルコール飲料を中心に、醸造からおいしさを生み出すことを目指しています。以前は私自身も研究者として「ビールの香り」をテーマに研究をしてきました。
具体的な研究事例を一つ挙げると、ワインはグラスをくるくると回して香りを楽しみながら飲みますよね。でもビールはグラスの上から匂いを嗅いでも香りがわかりにくい。実はビールの香りを感じるタイミングは、飲んだ後なんです。人間は飲み物を飲む前に息を吸い、止めた状態でごくごくと飲み、飲んだ後に息を吐き出します。プハーと息を吐いたとき、喉から鼻に戻ってくる香りにこそビールらしさを感じると気がつきました。
人間の口内環境を再現する研究を続けたところ、グラスから出てくる香りを直接分析した時と比べて、飲んだ後に20倍ほど強くでる香りを発見したことがあります。この香りは単独の成分としては、ポップコーンや枝豆の香りと形容されますが、ビールにとって重要な香りの一つでした。
このような研究によって「ノンアルコールビールを本物のビールに近づけるには、この香りを増やした方がいい」とか、逆に「ビールの苦手な人にはこの香りを減らした方がいい」といった具合に商品への応用が効くようになりました。
要は、会社からは「ビールを飲む時に喉から鼻に戻ってくる香りについて研究して欲しい」と具体的な課題を提示されることはなく、先ほどお話した通り、売り上げを伸ばしたいとか、もっと美味しくといった抽象度の高い要望がくるんです。
それに対して何を課題として設定するかは研究者自身に委ねられています。いかに具体的で解像度の高い課題を設定できるかが、研究開発における大きなポイントになります。
抽象的な問いに、短期間で応えるoutsight
「思考の筋トレ」が研究に活きる
ーーoutsightの導入のきっかけは何でしたか。
2022年に私自身がoutsightに参加したのがきっかけです。実際に受講して当社の研究者に必要な筋力を鍛えられると意義を感じ、所属長になったタイミングで導入を推進しました。
outsightでは毎週ベンチャー経営者から、比較的抽象度の高いお題が出されます。
「会社の象徴となるような新しいサービスを考えて欲しい」
「今ある商品の新しいマーケティング手法を考えて欲しい」
など、与えられるテーマが広いんです。
受講者はこのお題に答えるわけですが、ベンチャー経営者にいいソリューションだと思ってもらうには、前さばきが非常に重要になります。マーケットや会社の置かれた状況、経営者が抱える課題をしっかり把握したうえで「何を求められているか」を正しく理解する必要がある。それがうまくできていないと、的外れなソリューションしか出せないんですよね。
そしてこの構造は、当社の研究者が置かれている状況にかなり近い。会社から与えられた抽象度の高い課題に対して、自分たちで前提条件を整理して課題を設定して答えていくわけですから。
さらに当社の場合、研究は年単位で行われるためサイクルが長いのですが、outsightでは毎週新しいお題が出され、アウトプットが求められます。研究者に必要な課題設定力をはじめとする思考力を鍛えたいと考えたとき、非常に意義のあるプログラムだと感じました。私の部署では現在、メンバー全員にoutsightへの参加を推奨しています。

深掘り型の研究者に、視点の広がりが生まれた
ーー参加したメンバーからの反応を聞かせてください。
良い反応をたくさんもらっています。直近の参加者からは「自分が何について考えるべきか、意識的に思考のプロセスを考える癖が身についた」と感想をもらいました。
outsightでは、私たちとあまり接点のない業界のベンチャーも登壇します。こうしたケースは前提条件をしっかりインプットして、そもそも「何を考えるべきか」という切り口を整理しないことには、有益なアウトプットが出せません。
しかし現職では業界経験が長くなるにつれ、前提条件をしっかり整理しなくても経験である程度動き出せてしまう部分が多くあったと。今までおざなりにしてきた前提条件の整理が、スタート地点として実は非常に大切なことに気がついたという感想でした。
さらに「普通ではないアイデアを積極的に考えるようになった」という感想ももらっています。
outsightではベンチャー経営者が、これまで考えたことがなく、是非取り組みたいアイデアを「白星」、これまで考えたことはあったものの、取り組みに至っていないアイデアを「黒星」として評価します。
受講者は白星の獲得を目指して課題に取り組むわけですが、この「白星思考」が日々の業務にも浸透しつつあると。要は、マーケットに精通している人でも見つけられていない切り口をいかにして見つけるか。これはまさに、私が冒頭でお話しした「センスのいいリサーチクエスチョンを立てられるか」に通じる部分だと感じています。それができて初めて普通ではないアイデアにつなげられるのだと思います。
ーーoutsight参加者の変化について、野場さん自身が何か感じていることはありますか。
研究テーマを設定する際、以前と比べて視野が広がり、幅広い切り口で考えられるようになったと感じています。そもそも研究者は、深く掘り下げるのは得意ですが、横に広げるのは苦手な人が多い。さきほど解像度というワードを出しましたが、解像度を上げるには、切り口の幅広さと、深掘りの両方が必要と考えています。outsightで幅広いテーマに触れ、時に斬新なアイデアにも思考をめぐらせたことで、漏れのない発想ができるようになっています。
また、アイデアの発信に対するスタンスにも変化が生まれています。ブレストのような場では斬新なアイデアが求められますが、そうはいっても的外れなアイデアは出しづらいですよね。この点においても、臆さずにアイデアを発信できるようになってきている。白星を狙い続けた経験が、そのスタンスを醸成してくれたと感じています。

ーーファシリテーターからの学びも多かったと聞いています。
まさに。outsightではファシリテーターが思考方法を言語化して見せてくれます。たとえば、災害やメンタルヘルス関連のベンチャーなど、自分自身の専門から離れ、触れたことのない分野のビジネスを考える際は、どこから手をつけたらいいのかわからず止まってしまう。
そんな時にファシリテーターの方が、考え方の道筋を整理して説明してくれるんです。もちろん「ファシリテーターの思考方法が正解」というわけではありません。でも人の思考方法を知り、自分なりに思考を繰り返すことで思考の筋力は鍛えられます。自分なりの思考方法を定めていくうえで学びが多いと感じています。
ーー今後、outsight受講者に期待することは何ですか。
シンプルに言えば、自ら考え、自ら動くことによって結果を出す人になって欲しいと考えています。
当社では大学やベンチャーとコラボレーションをする機会も多いのですが、その際に大切なのが、研究者自身の「軸」や「専門性」です。メンバーには是非とも自分だけの研究テーマを見つけて特定の分野の専門家になって欲しいですし、同時に、解像度を上げて課題を設定できる、課題設定のプロになることでアウトプットを出せる人になって欲しいです。
outsightはベンチャー経営者の視点に触れて思考力を鍛える実践の場です。越境経験を実務に還元できる有意義な時間だと思うので、今後は社内の他部署にも積極的に推奨していきたいですね。
Fin
【outsight 無料体験のご案内】
outsightでは、9月限定で無料体験を受け付けています!2社のベンチャー企業の経営課題に触れていただくことができます。ぜひこの機会にご参加ください!
→ 詳細はこちら
協力:アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社
インタビュー・文:藤井 恵